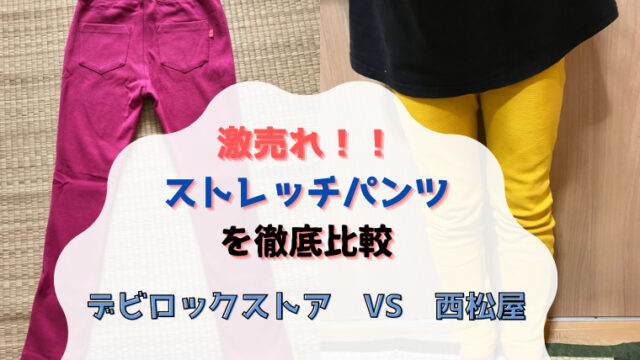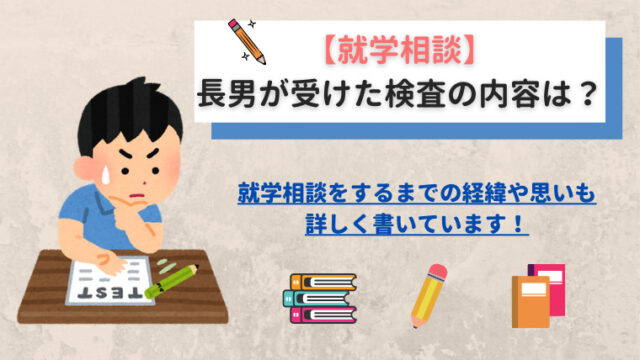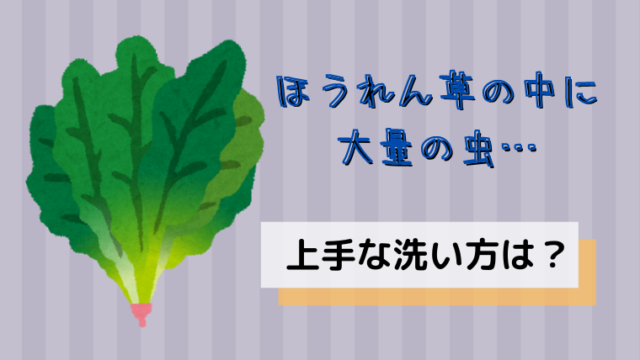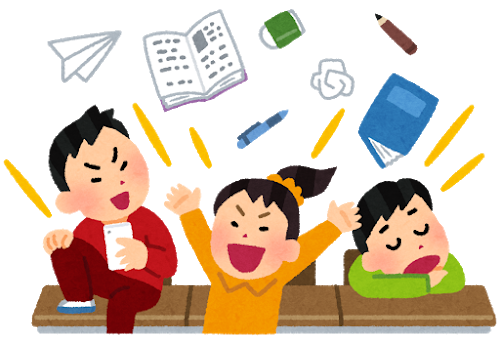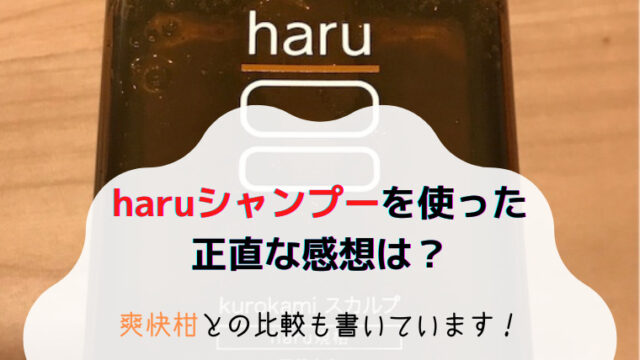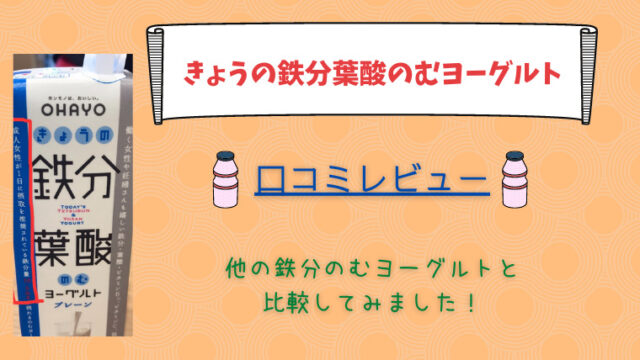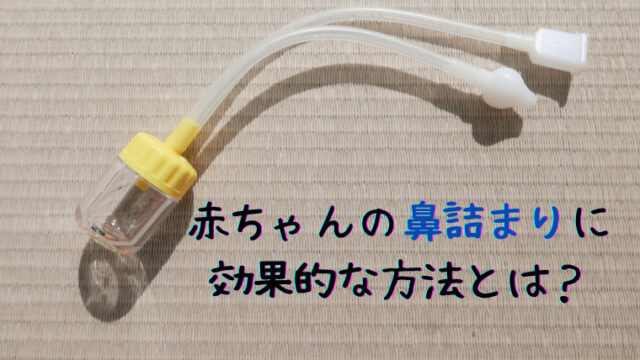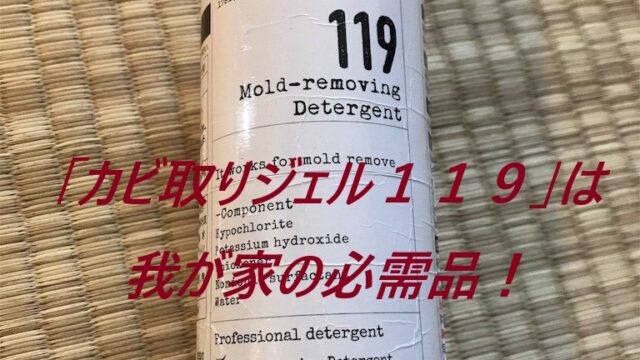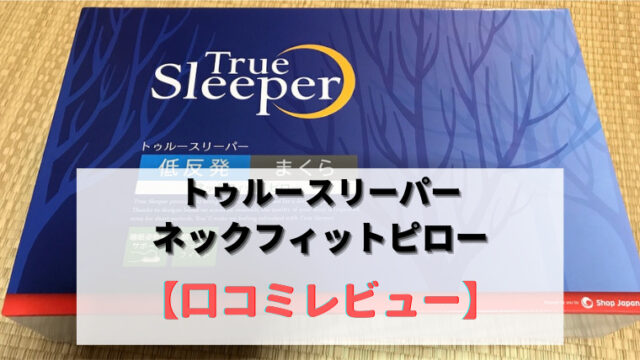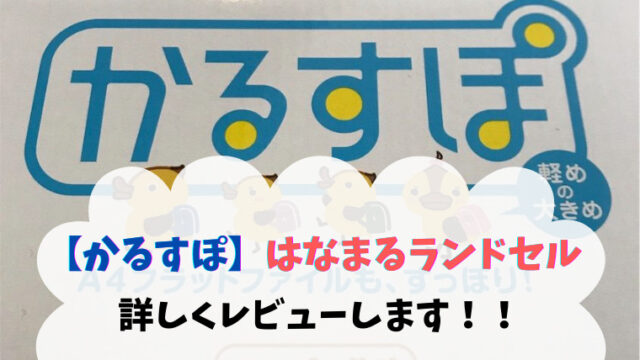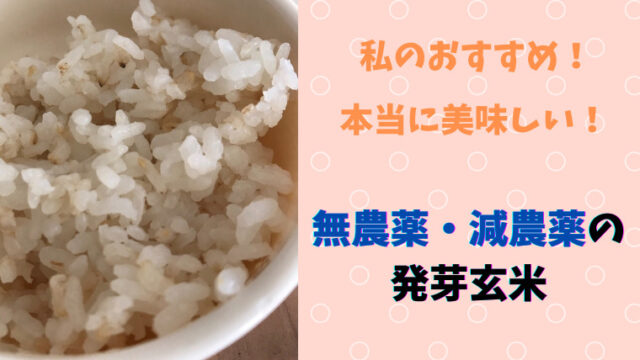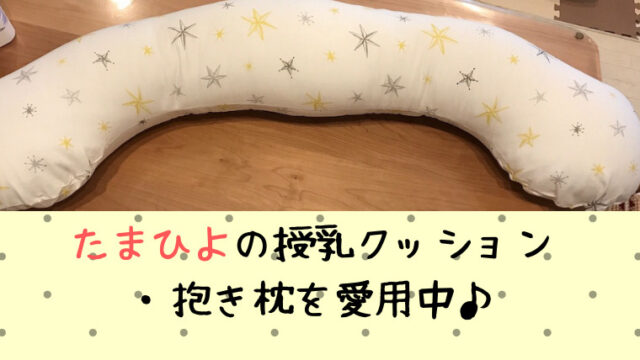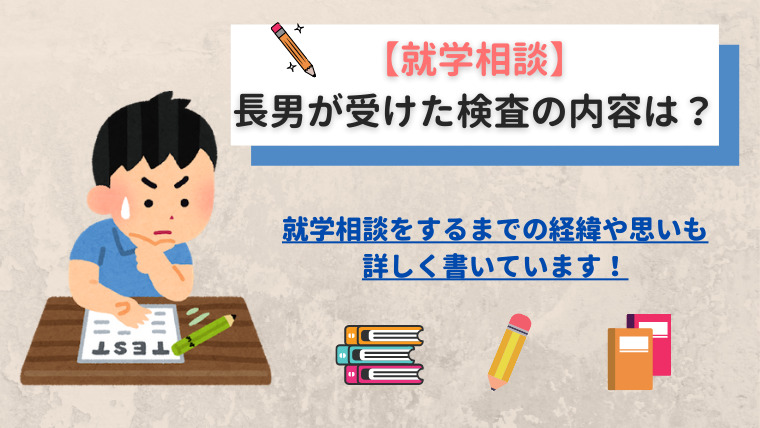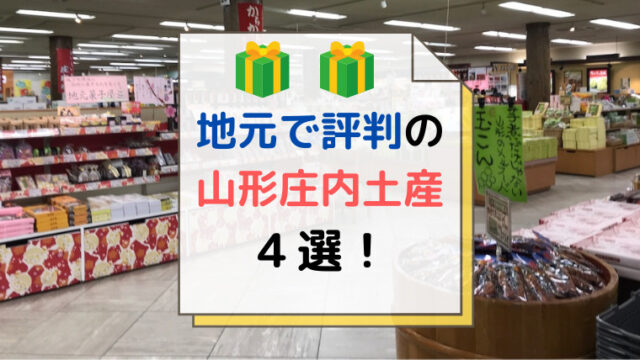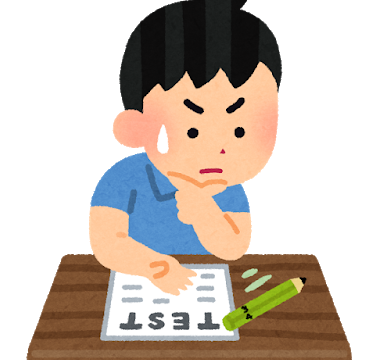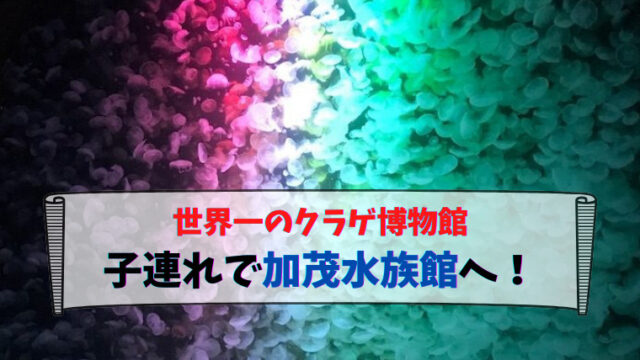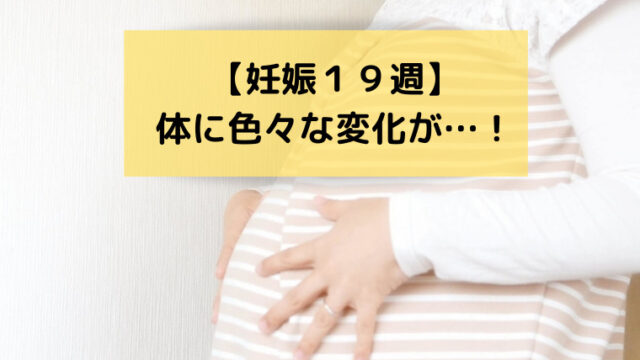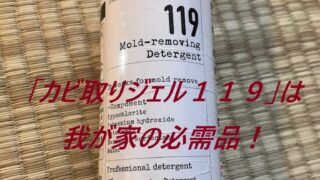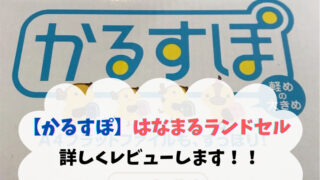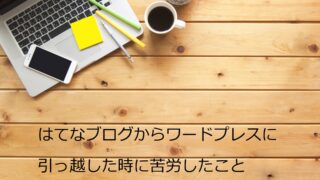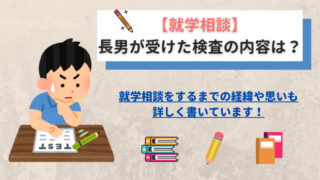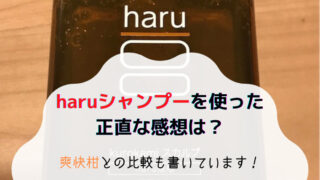こんにちは!
3人の子持ちママsaki(@saki3903)です。
就学相談をするまでの今までの経緯や思い
4年生の時のクラスが学級崩壊
今までの記事でも何度か書いてきましたが、うちの長男が4年生の時にクラスが学級崩壊し、それと共に、うちの長男も教室を出て行ったり、学習に取り組めなかったりと、色々な問題がでてきました。


本人の状態に改善が見られず、悪化していくばかりの日々
私も長男とよく話し合って、今度はちゃんとやろうと約束をしたりと、一緒にたくさん悩み苦しんできましたが、事態はどんどん悪くなるばかりでした…。

3学期になると「学校に行きたくない、つまらない」と言う日が多くなり、何日かお休みしてしまうこともありました。
本人は、とにかく担任の先生のことが嫌いだったので、先生とまともに会話することもできないし、信頼関係なども全くといいほどできていませんでした。
先生も諦めていたからか?2学期の算数ドリルはなぜか12月に渡されるし、3学期のドリルも3月になって渡されました…
先生は、「すみません、私が持っていました」「私、忘れっぽいので…」などど言っていましたが…。。
これじゃあ勉強なんてできないですよね…(-_-;)
そんなことまで言う先生なんだから、長男が嫌いなのもわかるような気がしていました。
学校で支援会議を行うことに~相談をすすめられる
私は、うちの長男がこんなにも変わってしまったのは、絶対に先生・周りの環境の影響が大きいなとは思っていたのですが、やはり学校側としては、本人自身の問題としかとらえてくれず…
2学期に、学校内で2回ほど支援会議を行うことになりました。

担任・学年主任・校長・教頭・特別支援学級担任・養護教諭・そして私…
あの~…6対1なんですけど…
配られた資料も、うちの子の悪い面がズラッと書かれていて、それを1から読み合わせて、「なんでここまでこの子はやる気がないの~!?」「多動・衝動性がある」「知的にも問題あるはず」など、色々言われて…
それでおしまい。
これからどうやって支援していくかの具体的な話はないのかな?って思いましたが。。
結局は、検査をしてくださいってことが言いたかっただけなんだなって思いました。
しかも、その資料、最後には回収されてシュレッターにかけると言っていたのですが、そういうものなのでしょうか、支援会議って…。。
資料はもらえないものなのでしょうか…
もちろん、教室を出て行ったりしているから、色々言われるのは覚悟はしていたけれども、とっても辛かったです…
私としては、長男は少し落ち着きがない元気なタイプだな、と前々から思ってはいました。
でも、3年生までは、教室を飛び出したりなどは一度もなかったし、授業も積極的に受けていたし、成績も良い方だったので、学校側から「相談しましょう」と言われることも一度もありませんでした。
なので、どうして4年生にになってこんなに急に変わってしまったのか、とても疑問に感じていました。
このままだと学校側との話が何も進んでいかないと思ったし、もし周りの環境が原因だとしても、ここまで本人が裏を返したように変わってしまうのは、やはり本人自身に何かしらの特性があるのかな…とも考えるようになったので、とりあえず、相談を受けることにしたのです。
巡回相談員の先生と相談
まずは、学校に定期的にいらっしゃる巡回相談員の先生と相談するように言われました。

その先生が言うには「検査をするのも1つの方法だけれども、この子の場合は周りの環境の影響が大きすぎる」とのこと。
その後、相談の先生から学校側に話をしていただいたりもしました。
小児科でのカウンセリング
その後、指定された小児科でカウンセリングをし、そこから、専門の病院(発達障害の治療などを行う小児科)への紹介状を書いてもらって行ってきてください、と学校側から言われました。
その指定された小児科は、運よく、いつものかかりつけの小児科でした。
昔からとってもお世話になっている素晴らしい先生なので、この先生に相談できるのはラッキーだなって思いました。

昔からよく知っている先生なので、こちらも話しやすいし、先生もとてもよく話を聞いてくださったのでありがたかったです。
すると、小児科の先生にも「この子の場合は周りの環境を整えることがまずは大事」と言われ、発達障害の外来への紹介状を書いてもらうまでにはいきませんでした。
しかし、3学期になり、長男の様子は悪くなる一方…。

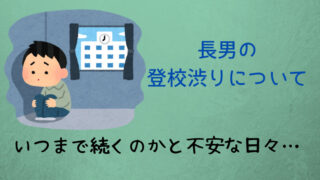
そして、やはり、本人自身にも何かしら問題があるのではないか…?という思いが、私自身だんだん強くなってきたので、そのことを小児科の先生にも話したら、「検査は受けてみても良いとは思うけれども、どうしますか?」と聞かれ、一応受けてみようかと思い、「お願いします」と答えました。
そして、その後の流れについてお話していただきました。
学校に「就学相談」の申し込みをする
小児科の先生がおっしゃっていた通り、まずは、学校の教頭先生に「就学相談を申し込みたい」と話をしました。
その後、検査をする場所を決めることに。
うちの地域の場合は、学校の空き教室か教育センターかどちらかを選んでくださいと言われました。
ただでさえ、学校に行きたがらない長男なので、学校内ではなく教育センターの方がよいのではないかと思ったので、教育センターで検査を受けることを希望しました。
ちなみに、検査をする日は、学校は出席扱いになるようなので、長男はちょっと嬉しそうでした。
私は複雑な気分でしたが…(-_-;)
就学相談の流れ・内容について
指定された日時に教育センターへ行き、就学相談を受けてきました。
プレイルームに案内される
まずは、色々な遊び用具があるプレイルームに案内されました。
長男が遊んでいる間に、親の私は、部屋の端の方にあるテーブルに案内され、まずは就学相談担当の先生とのお話がありました。
いきなり「特別支援学級への入級についてお考えなんですよね?」と聞かれたのですが、その時の私としては、入級とか、そういうことよりも、学校への不信感・4年生になって急に変わってしまったことなどを聞いてもらいたくて、ベラベラ話してしまいました…
でも担当の先生はとても親身にメモを取りながら聞いてくださり、「色々あったんですね。」と。
実際に行った検査内容
その後、担当の先生と長男が別室に行き、色々な検査をしてもらいました。
その間、私も色々と書くものを渡されました。
記述式のものもあったので、かなり時間がかかりました。
<保護者が記入するもの>
記述式。私は今までの経緯も含めて詳しく書きました。
予防接種を受けた日にちなども書くので母子手帳は必須でした。
子どもの日頃の様子から社会生活能力の発達を捉える検査です。
| 身辺自立 | SH | 衣服の着脱、食事、排せつなどの身辺自立に関する能力 |
|---|---|---|
| 移動 | L | 自分の行きたい所へ移動するための能力 |
| 作業 | O | 道具の扱いなどの作業遂行に関する能力 |
| コミュニケーション | C | 言葉や文字などによるコミュニケーション能力 |
| 集団参加 | S | 社会生活への参加の具合を示す能力 |
| 自己統制 | SD | 図形や数量の理解・処理といった数学的思考を含んだ、問題解決に向かって思考する力 |
このような、広い視点で子どもの社会生活の様子が測定でき、社会生活年齢が算出されます。
とりあえず、今のありのままの長男の様子について回答しました。
こちらは、親・養育者による他者評価形式を採用した検査です。
性格が形成される基礎段階にある子どもを客観的に把握し、養育上必要な配慮を見出すための検査です。
「顕示性」「神経質」「情緒安定性」「自制力」「依存性」「退行性」「攻撃性」「社会性」「家庭適応」「学校適応」「体質傾向」の11項目から診断する検査です。
・質問項目数139問
・「はい」「いいえ」で回答
・回答所要時間:20分程度
こちらも、今のありのままの長男について回答しました。
<長男が受けた検査>
今回、長男が教育センターで4年生時に受けた検査はこちらです。
5歳0月~16歳11カ月の子どもを対象にした、世界でも広く利用されている代表的な児童用知能検査です。
5つの合成得点(全検査IQ、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリ、処理速度)が算出され、それらの合成得点から、子どもの知的発達の様相をより多面的に把握することができます。
スイスの心理学者で産業カウンセラーのKoch,K.が1945年に創案した心理検査です。
検査方法は非常にシンプルで、1本の実がなる木を書いていくだけになります。
その中に投影される情報を、専門家が読み解いていく心理検査です。
自由に書いてもらった「一本の木」から、その人の持つものの考え方、思考のくせ、言葉で表現しにくい内面の気持ち、深層心理などを知るために役立ちます。
教育センターで受けた検査は以上です。
全部で2時間くらいかかり、親子共々、結構疲れました。

それ以外にも検査があったのですが、5年生になって環境が変わると検査結果も変わってくることがあると言われたので、5年生の5月に、学校の空き教室で行いました。
(5年生になったら学校に行きたくないという日が一度もなくなり、本人も学校内で検査してもOKとのことだったので)
<5年生になってから受けた検査>
対象:小4~6年、中学生、高校生
実施時間:小学校:40分ギルフォード博士が作成した検査を、日本版として翻案し、標準化した検査です。
性格を記述するための特性を12個にしぼり、この12の側面から個人の性格を診断します。
診断の結果は、性格を類型化したり、社会における適応と自己の内面における適応の高低でとらえたりする資料が出され、個人のみならず、学級などの集団の傾向をつかむのに役立ちます。
心身の不調や不適応状態になりやすい学齢期の子供たちに対して、最近の状況についてのいくつかの質問に回答するなかから、子供の現在の心の健康状態を客観的に把握して、適切な支援につなげていくための検査です。
SR(ストレス反応)・ST(ストレッサー)・SS(ソーシャルサポート)の3つに関してパーセンタイルで結果が出ます。
検査の結果&校内での支援会議
支援会議の中で結果について話をしてもらいました
5年生での検査が終わって2週間後くらいに、学校から「検査の結果が出たので話を聞きに来てほしい」との電話があり、学校に向かうことになりました。
私は、検査担当の先生と私だけだと思っていたのですが、学校に着くと、なんと支援会議の時のメンバーがそろっていて、ちょっとビックリしました。
支援会議をやるとは聞いてなかったので…(-_-;)
もう逃げられないので、意を決して支援会議に臨みました。

検査の結果を見ると…
私が思ってたよりも本人にはそこまで大きな問題がなかったので、ちょっと安心しました。
WISC-Ⅳ知能検査に関しては、言語理解の項目がやや低くなっていましたが、あとは平均~平均の上あたりだったので、特に際立った問題はなし。
M-G性格検査に関しても、やはり5年生になって環境が変わったからか、そこまで大きな問題はありませんでした。
情緒安定に関しては、なんと、かなり安定しているとの結果に…。
4年生の時にこの検査を受けていたら、確実に情緒不安定の結果だっただろうな…と思います。
環境の影響って本当に大きいのだなってことがよくわかりました。
PSI検査では、担任・友人関係への不安を少し感じているという結果でした。
これは予想通りでした。
判定をするかしないかについて
今回の検査結果を踏まえて、発達障害などの判定をするのかどうかを最後に決めることになりました。
判定をするためには、判定委員会?のようなところで、判定をしてもらうのだそうです。
検査担当の先生は、判定するのを却下しても良いのでは?という意見。
教頭先生も、同じ意見でした。
特別支援学級の先生も、その流れで、それで良いということに…。
そういえば、去年の支援会議では、特別支援の先生が一番、うちの子のことを「多動・衝動的だ、検査すべきだ」などと強く言っていたっけな…。
でもやっぱり、今回は、教頭先生も検査の先生も、判定しなくてもよいのではとのことだったので、同調したのかなって思いましたが…(^^;
長男自身も、支援級に行く気がなく、今のクラスでやっていきたいという思いがあるので、判定はせず、このまま今のクラスで支援しながらやっていくという方向に決まりました。
支援級に入らなくても様々な課題のある長男
支援級に入らないことにはなったのですが、今でも様々な課題がある長男…。
〇授業中に教科書やノートは出さない(4年生からのことを引きずっているのかもしれませんが…)
〇自分で「無理」と思ったら、何を言っても絶対にやらない(宿題・プリントなど)
機嫌が悪かったりするとテストなどにもほとんど取り組めず、くしゃくしゃに丸めたり、適当に回答したりするので、0点や5点になります…
気持ちが乗れば、90点以上取れる時もあるのですが…
担任の先生も、うちの子のことをつかむのが難しいようで、「またこういう支援会議は定期的にやってもらえるとありがたい」と言っていました。
なので、支援会議はまた定期的に行うことになりそうです。
私は本当はあまり行きたくないんですけどね…^^;
でも、4年生の時のように、集団で教室を飛び出したり、学校に行きたくないという日がなくなったし、給食当番・掃除などの当たり前のことが普通にできるようになったということが、とにかく大きな成長だなって思っています。
もちろん、まだまだ本人の課題はありますが、全てがいきなり全部できるようになるとは思ってはいません。
親としては、どうしても「早くこれもできるようになってほしい」と思いがちですが、本人の成長のペースもあるので、ちゃんと見守っていけたらいいなって思っています。
今回はかなり長文の記事にになってしまいました^^;
最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m
ランキングに参加しています!クリックすると投票が入る仕組みになっています。
更新の励みになりますので、ポチッと応援お願いしますm(__)m
⇩⇩⇩
⇩⇩⇩
にほんブログ村
私が実際に購入して良かったものを紹介しています⇩